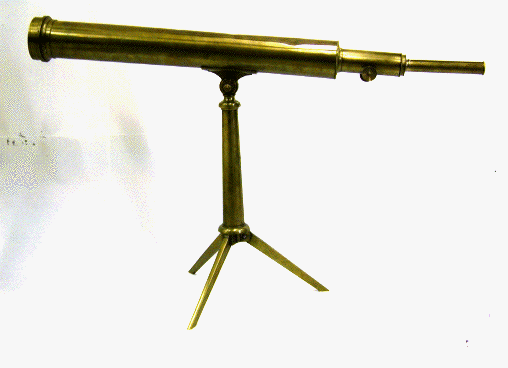
昔の望遠鏡-・
今回の5台の望遠鏡は、すべてブタベスト(ハンガリー)で手に入れたのですが、その中で、これが最も高価で十万円でした。
外観を見た限りでは一番単純な作りで、貧相で、ボロで、おまけに接眼パイプが
ぐにゃりと曲がってしまっています。更に、中をよく確かめると、なんと対物レンズはシングルレンズです。加えて、像はひっくり返って見えました。
そんなモノですから言わばガラクタの粗大ゴミにしか見えません。これが十万円ですからトンデモない値段のような気がします。------そんなガラクタが何故高価だったのだろうか?。
ここで、最も注目したのが、対物レンズの直径が73ミリで 5台の中で最大だという点。もうひとつ、倒立像だという点、この2点から、この望遠鏡は使用目的を天体観測に置いていた、と判断しました。高価だったのはその辺に理由があった筈なのです。
-----とすると、この製品は一体いつ頃作られたのか、それが問題です。
望遠鏡はガリレオによって発明され利用されるようになった、と、一般的にはそう云われています。確かに、ガリレオが「テレスコピオ」という望遠鏡の正式名称に合意したのが1611年なので、その時から望遠鏡は天文学を研究するのに必要な科学的な器材として位置づけられたと考てよいと思います。つまり、望遠鏡が科学の名に於いて最初に認知されたのがその時からなのです。それだけははっきりしています。
然し、科学の名に於いて認知される以前に、よく調べてみると、望遠鏡は既にかなり広く使用されている事が判りました。但し、それはオモチャであっただろうし、中にはいい加減なシロモノも含まれていたかも知れませんが、そればかりではなく、オモチャでもよい、理屈などどうでもよいから---との客からの要請で、軍人は遠くの敵軍を発見するため、船長は遠い島影を見るため、貴族は馬車でドライブする美しい女性を眺めるため--etc、と、とにかく市場の要求を満たすため相当量作られていたと推測されています。
そんな事実から、望遠鏡の発明者はガリレオではなく、それ以前の オランダのハンス・リッペルスハイ、が最初であったとされています。
1600年を少し過ぎた頃です。(1600年となると日本では関ヶ原の戦いの年です。)この頃の望遠鏡は
勿論 シングルレンズの組み合わせで作られたガリレオ式でした。
然し、シングルレンズの屈折望遠鏡には色収差があるという事で、御承知のように、ニュートンによって色収差の無い反射望遠鏡が考案されたのをキッカケとして(1668年)レンズによる望遠鏡の製作は当然ながら下火になった、と、ひとまず考えられます。但し、その後、ガリレオ式からケプラー式に変わり、更に 色消しレンズの発明により巻き返しが起き 再び屈折式望遠鏡が脚光を浴びるようになりました。屈折式は小型機に於いて、 以前からのシングルレンズ方式を底辺で引き摺りながら、再び全盛期を迎える事になったのです。
望遠鏡に色消しレンズが最初に使われたのは、1758年オランダのドランドがイギリス王立協会に寄贈した時、と云われています。望遠鏡が発明されてから約150年後、ニュートンの反射式望遠鏡の発明からもざっと100年後です。
残念ながらその色消し望遠鏡がどんな形をしていたのかは判っていません。
(以上、参考--斎田 博 著『おはなし天文学』)
----ここからは推測の範囲になります。
望遠鏡の歴史には確かにいろいろと変遷がありました。然し、その変遷の歴史を考えるとなると、まず、かなり長期にわたっている事と、オランダ、フランス、イタリー、そしてイギリス、ドイツ、と、ヨーロッパ全域をカバーしての地域的な推移を見る必要がある事、当然ながら各地での動きが同じではなかったという事、つまり、一本調子で進んだわけではなく複雑にそして[ふくそう---この漢字が出ませんネ]しながら進んで来たという事、----このあたりを踏まえると、簡単には、時代に線引きが出来ないのでアンテイック製品に対しては軽々しく時代の断定も出来ない、という事になります。
申し上げたい事は、最初の望遠鏡の発明から、その後の、反射鏡の発明、色消しレンズの発明、それらがあったにせよ、シングルレンズの望遠鏡は底辺では根強く生きて完全消滅せずに生き延びてきたであろう、という事です。なにせ安く出来たのです。大衆にも容易に入手出来たのです。或る程度の我慢が要求されるにせよ、全く使えない訳ではありませんでした。かってガリレオが観測した月の噴火口の様子、金星の満ち欠け、土星の環の変化、木星の衛星、太陽黒点の状況、部分的ではあっても星雲・星団の姿、これらの初歩的観測には立派に役に立ったのです。庶民にとっては、それすら驚きで迎えられた時代が長く続いたのです。
最初の望遠鏡は手持ちで見る簡単な「遠メガネ」でした。然し、少なくとも天文観測となると、それでは具合が悪いので、必要な装置がおいおい装着されるようになりました。模範になったのは当時の高級色消し天体望遠鏡だったと思います。今回
取り上げる製品はそこまで進化した高級な?ケプラー方式のシングルレンズ天体望遠鏡なのです。時代はかなり後、思い切って推測すれば1800年前半、もしかしたらもっとあとかも知れません。
(但し、ここでは、とりあえずの断定だとしておきます。)
こうなるとシングルレンズ仕様とは云え、ガリレオ時代とは比較にならぬ程に優れた性能を有していたと断言出来ます。
ガラクタにせよ高価なのは目的をキチンとわきまえて作られた製品、その辺にその理由があります。
重ねて申し上げますが、とりあえずは独断と偏見で、そう申し上げておきます。
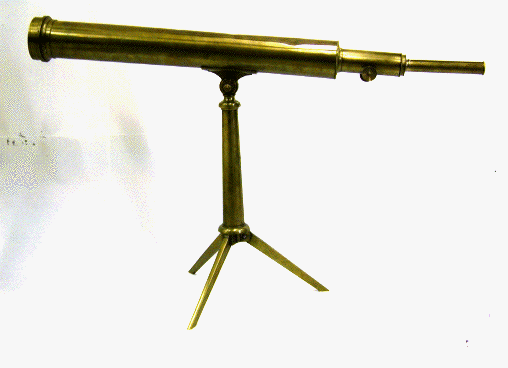
この望遠鏡は総真鍮製です。
因に、真鍮とは銅と亜鉛の合金、別名「黄銅」です。似たような金属に 砲金、別名「青銅」(ブロンズ)があります。砲金とは銅と錫の合金で高価ですが、それに比べて真鍮の方が値段がぐっと安く又
加工がし易いのが特長です。
真鍮は砲金より後になって主に使われるようになりました。かなり最近からです。従って、この望遠鏡は、当時としては新しくそして安価な真鍮を部材の材料として選んでいるのが分ります。
見え味はどうだったか?。----残念ながら、接眼部ドローチューブが曲がっているため完全な判断は出来兼ねる状態でした。然し、敢えて申せば、まずは<素晴らしい見え味>だったと申し上げておきます。
このレンズ系は一個の対物レンズだけでなく、ドローチューブの対物レンズ側先端に凹の補正レンズ、つまりエクステンダーレンズ(バローレンズ)が装着されている事です。鏡筒を長くしないで、なおかつ全長を短くして焦点距離を長くし、それによってF値を大きくし色収差を少なくしたかったのだと考えられます。更に
操作性もよくしたい、と、この意向もあった筈です。シングルレンズ系としては理に適っています。ここまで配慮してあるのですから、シングルレンズの天体望遠鏡としては高度のモノです。同じシングルレンズ望遠鏡ながらガリレオ時代のガリレオ式とは大きく違った仕様で、それだからこそ実用品として活躍出来たと思われます。多分、それなりの量産が達成され、相当数売れたヒット商品だったに違いありません。
唯、本当に残念なのは、せっかくの補正レンズを装着した新機軸の優秀品でありながら、ドローチューブを一杯に繰り込まないとピントが合わない点でした。
この望遠鏡の全長は870ミリ、重さは約5キログラム。大きさは現在の市販望遠鏡クラスで全く問題のない大きさです。
---------------------------------------------------------
実は、ここまでは通り一遍の「賛辞」に過ぎません。問題は山積していたのです。
この望遠鏡が、どこかおかしい、と感じた最初は--------
上の写真を見て下さい。ここではドローチューブを一杯に縮めた状態にして写してあります。つまり鏡筒はこれで最短です。前に書きましたが、この状態で無限がやっと見えます。----まあ、それはよいとして、思わずも気が付いた事は、この望遠鏡では天頂が見られない、という不思議な構造に驚いたのです。鏡筒を天頂に向けようとすると接眼部が床に当たってしまうのです。そんな天体望遠鏡ってあるのだろうか?。
もう一つ。この望遠鏡の見え味は凄くよい、と、先に書きましたが、念のため倍率を計ったところ、なんとこの天体望遠鏡の倍率はたった15倍なのです。倍率は勿論固定ですからそれ以外の倍率は選択出来ません。これでは惑星の形姿を確かめる事は出来ませんね。
参考までに、対物レンズの口径は、レンズ裏側の金物で多少カットされているので、正確には71ミリでした。接眼レンズを通して見たヒトミ径が約5ミリ、接眼レンズの焦点距離は約55ミリ、これを逆算すると対物レンズの焦点距離は約800ミリ(補正レンズを含む。)です。
接眼レンズは察するところ絞りがレンズ間にあるのでハイゲンだと思います。何故ハイゲンなのか、ラムスデンではダメだったのか---そうも感じましたが、焦点距離が長い事でアイ・リリーフを短くしたいため、その理由でハイゲンにしたとすれば納得します。
中の補正レンズはどんなモノか、それは、開けてびっくり!!なんと凹凸の合わせレンズでコート付の現代産の凹レンズでした。更に、これも念のため、接眼レンズをバラしてみたところ、こちらも元玉
レンズ開き玉 レンズ共々凹凸の合わせ玉でした。
この望遠鏡の見え味は良いにしろ、視界は目見当ながら10度はありません。まさに「葦(よし)のズイから天井覗く。」の狭視界です。
更に驚くのは、対物レンズ枠が5個の金物で成り立っている事でした。そこで使用してあるビスの数は合計で12本あります。レンズはシングルですが、正確に光軸調整が出来るような構造になっているのです。どうして そんな立派な対物レンズ枠を考えたのだろうか。
こうしてみると、この望遠鏡は何度かの改造を経て現在に至っている事が分ります。然し、もともとはいつの時代のモノなのか。前述では1800年前後と申し上げましたが、これにも自信が持てず ゆらいで来ます。全体のイメージをその目で見ると、その、こなれた風体から、もしかしたら、1800年どころか、1900年を過ぎて作られた製品ではないのか、とも思ってしまいます。明治ではなく、大正か、場合によっては昭和か、となってしまいました。
こうなると、あれこれ申し上げてもキリがありませんので、多分、こうではないだろうか、と最初に仮説をいくつか立てながら展開を追ってみる事にしました。
・この望遠鏡は、1800年初頭の頃、色消しレンズ装着の高性能天体望遠鏡として誕生しました。
その時は、ぐにゃりと曲がっている箇所の細い接眼パイプは無く、その根元のドローチューブ側に直接
複数の接眼レンズが取り付けられるようになっていました。補正レンズは必要がないのでつけてはありません。構造としては現在の製品と全く同じです。
製品はメーカーズアジャストで対物レンズの光軸調整が為された状態で出荷されていました。光軸調整はユーザー側ではやれませんでした。
構造的にユーザー側ではムリの設計になっています。レンズの芯取り精度不足、研磨上がりでのニュートンリングの不規則な偏り、などがあって光軸調整はメーカー側にとって絶対条件だったのです。
対物レンズの有効径は70ミリ。焦点距離は700ミリ。F=10 の丁度良い選択でした。接眼レンズは多分ラムスデン10ミリと20ミリあたりが無難だった筈です。別途に、アフオーカル系の像反転レンズ、それに加えて、今回のに付いている長焦点距離の接眼レンズ、但し、レンズはシングル。従ってミリ数は違っていたと思います。又、絞りは適当に大きく30〜40度程度の視界が得られるようになっていたでしょうね。---これは、像反転レンズとセットで地上用に使用するものです。
(その他、サングラス、又は投影板、天頂プリズムかミラー、等々。 但し、これ等は今回の考察には直接必要ないので論評はカット。)
この天体望遠鏡は、その筋へ献納されたり、又は依頼されての納品だったり、今で云う受注生産品で作られていました。
・然し、 70ミリ色消しレンズ仕様となると余りも高すぎて受注生産と云っても高すぎて依頼も少なかったと思います。(参考までに、東京天文台には1800年頃輸入された当時の望遠鏡が倉庫から発見された
との新聞記事が出ていました。その製品の口径が確か70ミリでした。70ミリは決して小口径ではなかったのです。)勿論、受注生産ですから在庫一掃のアウトレットセールなどは発生しません。然しとにかく売れないのでは困るわけです。勝手な想像では一台セットで当時
現在価格で百万はしたろうと思いますね。-----これではダメ、せめて数十万で売れる製品という事で急遽?開発された?のがシングル対物レンズを使用した上記の望遠鏡の安価版でした。付属品等はすべて同じ。但し、これでもあまり注文は取れなかった筈です。それは、対物レンズのF値が短すぎて、色収差が酷すぎたためだと推測されます。
このあたりは1800年後半だと位置づければ合いそうです。
少し方向を変えて考える事にしてみますが------一般的なモノを売る商店が出現するようになったのは、1900年直前あたりからで、それに火をつけたのが1900年に開催されたパリ万博でした。この世に商店街が出来たのはパリ万博以降です。それまでは商店街などという庶民を相手にした店などはなかったのです。
シングル対物レンズの天体望遠鏡は、徹底的に庶民を相手にした商品でした。光学器械であれ店に並べて客を待つ時代になって来たのです。 この時代になって始めて、売れなければ
改良してでも売れるようにしなければなりませんでした。アウトレットのハシリが出たとすればこの辺からでしょうね。
------という事で、この望遠鏡にも改良品がいろいろと出てきたのです。それが下の・になります。
・色収差をいくらかでも少なくしたいとの要求から、凹の補正レンズを入れました。但し、このレンズはシングルです。本来なら対物レンズ径を小さくすれば
ある程度は解決するのですが、製作者側はそうはせず、接眼レンズの視界を或程度狭くする事で分解力及び集光力はそのまま保持出来るようにしたのです。
凹レンズを入れた事で全長が長めになりました。但し、接眼レンズをつけた状態で、天頂に向けた時、接眼レンズが床に当たらない範囲です。
・これで、ひとまず解決したのですが、やはり問題は色収差でした。まだまだ残っていたのです。
然し、どうにもこうにも改良する箇所が見あたらなくなってしまいました。
そして数十年、時代はもう1900年の半ば頃の事でしたが、それを解決しようと頑張ったのが素人のユーザーの一人だったのか、それとも、とある機械加工メーカーで働いていた従業員の一人だったか、ともかく、目の前にある一台を自分なりに改良してみようと工作機械を使ってやり始めたのでした----それが現在ある現物だ、という次第なのです。
まず、補正レンズの凹レンズをコーテイング付きの色消しレンズ(アクロマートレンズ)に代えてみました。それによって色収差を幾分かでも少なくしようと考えたのだと思われます。改造者がどの程度
光学知識を持っていたのか分りませんが、アクロマートレンズを入れる事で収差が少なくなると考えたのは間違っています。対物レンズがシングルであれば、補正レンズでその収差を打ち消すとしたら同じシングルの凹レンズにしなければなりません。アクロマートでは収差はキャンセルされないのです。
そこまでやるとしたら、補正レンズをアクロマートレンズにせずに、対物レンズそのものをアクロマートにすべきでした。
とは云え、価格の点でそれが不可能だとしても、補正レンズをアクロマートとしては全く意味がありません。
加えて、そのために対物レンズの合成焦点距離が狂ってしまい、ドローチューブのラックの位置を変更せざるを得なくなり、大変な手作業で改造しているのです。従って
現品のドローチューブの上面には、最初のラック用の細長い穴があけっぱなしのままにされてあります。
----ともあれ、どうしたか?。結局、倍率を下げると同時に、接眼レンズの視界を思い切って更に小さくするほかありませんでした。地上用として用意されてある焦点距離の接眼レンズを改造し、アクロマートのレンズを組み合わせ
成り行きで55ミリという常識外の長い接眼レンズを特別作り(当人はそれが何ミリだったか分らなかったとは思いますが・・)視界環の径を数ミリにしたのです。これによって全長が思いもかけず長くなってしまい、天頂が見られなくなってしまいました。これは予期せぬ結果だったと思います。然し、苦心惨憺しただけあって、ともかく色収差は気にならない程小さくなりましたが、倍率が余りにも小さすぎ、天体観測には到底使い物にはならなかったのです。もうギブアップです。彼は近所の古道具屋に持ち込んだのです。古道具屋のオヤジが払ったのは(多分)煙草一箱分の小銭に過ぎなかった筈です。
念のため、現品の接眼レンズを外し、各種LVワイドを使って見たところ、この対物系では各収差がひどすぎて見られるシロモノではありません。視界を数ミリに絞った事で、確かにその範囲では良く見えましたが、それが限界でした。
これが現品です。
この天体望遠鏡が、最初のままの姿で売に出されているとしたら、その価格は現在ですら百万近くはしたろうと思います。しっかりした資料としての価値を持つからです。
とは云え、現品は 途中でいろいろ手を加えたにしろ十万というのは高くはありません。妥当な値段だと考えられます。
※ 因に、この望遠鏡の鏡筒に やや大きな花文字で Tlofs in Wien と刻印されてあります。この中で O にウムラウトが付いているので、ドイツ語だと云う事が分かるのですが、詳しい内容は不明です。
それにしても、面白い望遠鏡でした。まるでコロンボよろしく、いろいろと謎解きが出来たからです。その結果が正しいのか間違っているのか現段階では判断つきません。然し、まあ、当たらずとも遠からず、とは思っていますが?・・・・。