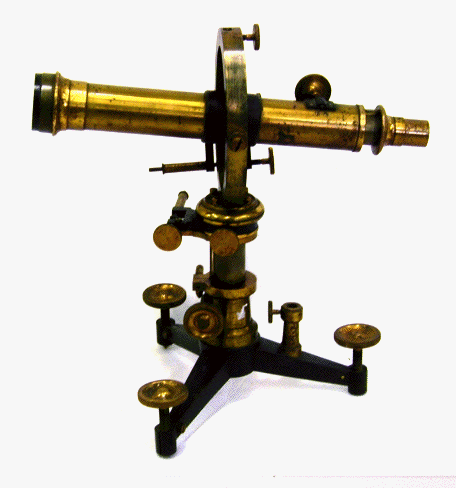
昔の望遠鏡-・
ビクセン光学の手元には現在5台のヨーロッパ製クラシック望遠鏡があります。ここでは、その5台を適当な順番で順次取り上げて御披露していきたいと思いました。
然し、 当然ながら、由緒のありそうな天体望遠鏡よりは、素性も使用目的もはっきりしない検査望遠鏡が多いのはやむを得ません。
そんな事で正確な記述はちょっと不可能のような状況にあります。従って、ここでは主として構造から見た機械加工からの視点と、外観からくる印象や感想を含めてイメージ的に取り上げざるを得ませんでした。
なお、多少の脱線はサイトの性格に免じて、前もって 許して頂きたいと申し上げておきましょうか。
最初に取り上げる望遠鏡は下記の製品です。
まず、ざっと眺めてみました。下部三脚その他2〜3点が鉄鋳物である外はすべてピカピカの砲金(青銅)製です。重さは6.3kg。例えて云えば、7倍50ミリ双眼鏡6台あまりの重量で、片手で持ち上げるにはかなりの重さでした。
鏡筒の全長は約390ミリ。望遠鏡としては小型の部類です。然し、大部分が挽きもの、つまり旋盤やフライス盤を使って削り出した機械加工部品の組み合わせで出来ています。アルミやプラスチックの型モノ加工部品に見慣れた現在の視点からは壮観というほかありません。見事な製品です。
鏡筒の真ん中の鏡筒帯に HARTMANN & BRAUN A.C. FRANKFURT A. M. No.988
-----以上のように刻印されてあります。ハルトマンですから、ハルトマンテスト、つまりハルトマン式のレンズ収差測定のための検査望遠鏡、これだと思いました。多分これに間違いありません。
ハルトマンテストについては、光学参考書に多くの記述が載っていますので、ここでは詳しい説明は省略します。
一方、ブラウンの名も気になりました。何かしら光学関係に貢献のあった学者のような感じがしたのですが、文献には書かれてありません。ドイツにはブラウンの名が多いので(有名なのはフオン・ブラウン博士、など)、単なる資本家だったのかどうか、続けて調べていきたいと思っていますが・・・。
推測(憶測を兼ねて)では、この器械は1900年初頭の頃の製品ではないかと思われます。ハルトマンがこの方面で論文を発表したのが1900年及び1904とあります。従って、それに対応して実際の製品を出したのは その少しあと、そう考えれば間違いありません。
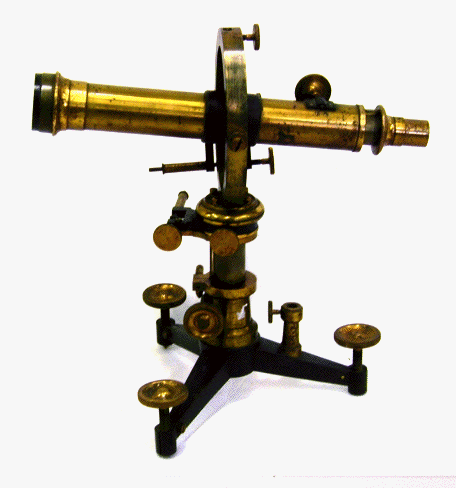
この望遠鏡の対物レンズの口径は40ミリ、倍率は約19倍、見かけ視界 約40度。至近距離1.6メートルです。検査用ですから像は倒立です。 点像を見た限りでは
そこそこで全面フラット、周辺の崩れも目立ちません。ドローチューブ内の内面反射が気になる点を除けば景色の像もシャープです。
まず気にした点としては、レンズ設計はどうやって行ったのだろうか?。----これがあります。
レンズ設計は厄介な設計です。多分、 その頃はペンで紙に書いて筆算でコツコツと何日もかけてやったに違いありません。
それに加えて、折角やった計算を他人に知られないように暗号で記録していたとか、特許に申請しても受け入れられず絶望したとか-----とかの、悲喜こもごもの歴史があったと文献には載っています。
戦後間もなくの頃の日本にはメカで動く計算機(例:タイガー計算機)など、一見タイプライターのような形で手で回して使う器械があったので複雑な計算も結構こなせるようになっていた筈ですが、100年も前となるとそんなモノも無いわけですから、さぞや大変だったと思います。
この場合のレンズはハルトマンが計算したのかどうか、知る由はありません。ただ、誰がやったとしても、口径がいくら、焦点距離がいくら、と簡単に云うものの、その裏での脳細胞の葛藤は複雑怪奇で、
推して知るべし 物凄い作業になった筈だと、つくづく同情するキワミです。
それに加えて、この場合は、他のレンズの良し悪しを判断するための基本レンズになるわけですから
更に大変な作業が必要だったと思われれます。然し、そのためもあってか、当時としては
かなり上等なレンズに仕上がっているのは頷けます。
この時代はレンズの研磨も大変でした。その大変な作業を経て出来上がったレンズは取り扱いそして組付にも万全の注意が必要だった筈です。
そのせいか、レンズ装着はすべて「かしめ」の方法をとって固定してあります。対物レンズを後から鏡枠に入れ、押さえリングを圧入してその後端を全周かしめています。現在ではネジを切った押さえ環を捩じ込んで固定しますが、当時
何故わざわざ かしめ の方法に固執したのかその理由は正直のところ理解出来ませんでした。かしめ方法では締め加減が不安定で、締め過ぎの懸念、逆に、締め不足にいるガタの心配、これらが付きまとった筈です。然し、それを承知でなおかつ慎重に行って組み付けを完成させた点に当時のマイスター達の心意気とプライドがあったのかも知れません。
接眼レンズも同様にかしめて固定してありますが、この方は日本でも戦前まで広く行われていたので、それなりの利点があったのだと思いますが、面倒臭いのと、歩留まりが悪過ぎるという理由から現在では全く行われていません。
対物レンズにはフードがついていた筈ですが、現品にはついていませんでした。
ドローチューブ繰り出し用のラックピニオンは上向きに位置しています。下に取り付ける現在の方法からみると一見異様なスタイルです。
然し、当時は踏襲されたきた技術の蓄積はそれほど多くないわけですから 上、下、又は側面であれ、どこでもよかったのです。逆に、現在は蓄積が多すぎるせいで、下向きと
硬直的に決め付けている方がむしろ異様なのかも知れませんね。
鏡筒の内部、ピニオンの下側に、ドローチューブのガタを防ぐために2枚の板バネがついていて滑りがスムースになるよう配慮してあります。 我々の場合はピニオンとラックの噛み合わせをキツくして調子を出していますが、その方法では噛み合わせのピッチ円を無視したやり方なので、本来は噛み合わせは軽くしてピッチ円を合わせ、バネを使って硬さの調子を出す方が正解です。その方法が優れているし理に適った方法と言えます。
接眼筒の両サイドからセンターをよぎる形で小さな数ミリの楕円の穴2個があけてありました。そして、その穴を外側からカバー出来るようにわざわざスライド出来るリングが嵌めてあります。-----これがわかりませんね。必要に応じてスケール用の糸などを穴を通して入れたかどうか----それにしても、穴の位置は接眼のピント面からずれているので理解が出来ません。
接眼枠をそっくり接眼筒に圧入した形跡があるので、その時必要になる道具類を引っ掛ける穴だったのか、そんな気もしたのですが、それだと接眼レンズを何故二重の金物にして装着する必要があったのか、それも分りません。とにかく何でもないような箇所に複雑なシカケを講じているので、ハルトマンは一体何を考えていたものやら、と思いますよ。何かにこだわっていたのでしょうね-----無論
分る筈はありませんが。
ともあれこの接眼レンズまわりは分解不可能です。何故か、場違いなまでにチョー頑丈に出来上がっているのです。
鏡筒は真ん中あたりで、大きな砲金の楕円枠のセンターに位置するように取り付けてあります。(写真では、ほぼ真横から写しているのではっきりしませんでしたが。)この楕円枠があるので、天頂は観測出来ず、従って、この望遠鏡が天体観測用でない事が分ります。
その、枠ですが、楕円ですから旋盤でスイスイと削り出す事は出来ません。材料とした砲金はムク材であれ鋳物であれ、加工となるとフライス加工でないと出来ません。どうやって加工をしたものやら、現在、もし同じ加工を汎用フライスでやるとしたら十万円近くはかかります。恐ろしい事です。当時はモノさえちゃんと出来ればそれでよし、それが なんぼで出来るか、とか、コスト意識など全く意に介せず、ドイツ人ですから、徹底的に頑張って「出来た、出来た、ホレ見たことか!。」と歓喜の声をあげ、ゲルマン魂を鼓舞させたに違いありません。
この望遠鏡には上下、左右の微動装置、そして鏡筒そのものを上下させる昇降装置、更にベースを水平にするための調整装置、これらの装置が完全に装着されてあります。それらの装置そのものの機構は、現在にも引き継がれているので何等の違和感もありません。
-----それにしても、それらの装置は こまかいなりに良く出来ています。精密器械ですから当然の事とは言え、アッパレなものです。我々が手掛けているすべての装置の原形をここに見る事が出来るので、我々の先祖の姿を目のあたりに見た感じになります。
更に 先祖の仕事で感心するのは----
現物を見て判る通り、この器械には多くのツマミが付いていて、それぞれが役目を果たしているのですが、そのツマミはすべて砲金のムク材から一体で挽きおろしたものばかりです。ネジはネジ、ツマミはツマミとして作ってドッキングさせたものではありません。因みに、現在はネジは既製品、ツマミはプラの
これも既製品を使うので、いかなる形状のツマミであれ簡単に手配出来ます。然し、当時は一個々作ったわけです。不経済きわまりない代物です。ただ、これも実際に使ってみて始めて分るのですが、手で回そうと加えた力がそのままネジの先へ正確に伝達されるので、微妙な調子や加減が実によく伝わって来ます。更に、それらの微動を制限するクランプ類も
小さいのに実に小気味よくキチキチと利くのです。現在のツマミ類はクランプを含めて、何となくグニャグニャするので、違いは明らかです。(我々にはアタマが痛い点ですよね。)
分らない点も何箇所かあります。
古いものだけに器材の中に欠品があるのは仕方がないのですが、何箇所かの、何かを装着させるための穴、ツマミ類、が疑問点として残されました。この状態では、一体何に使うためだったのか、その一つは水準器用ではないか、とか、いろいろと憶測や推測を重ねたのですが、正確には分りませんでした。まあ、止むを得ません。
又、ベースから上に伸びる昇降軸のやや太いパイプが何故か途中で つないであるのです。挽き目が見事なので、ちょっと分らなかったのですが、まさか途中で材料が不足して継ぎ足したわけでもあるまいに、と考えるのですが、何故そうやったのかその意図は全く掴めませんでした。
いずれにしても、この製品は 光学機器が成熟期に達した年代、つまり1900以降の作品ですから
見た目ではクラシック調に見えますが、それほどムカシの製品ではありません。
製作した方では、完全に機能本位に設計した筈で、特別にデザインに配慮した痕跡は見られません。勿論それでよかったわけです。
本来なら、無意識的にも、気持ちの入れ込み次第で美的観点にも留意すると思われるのですが、当時の愚直なまでのドイツ人にその余裕があったとは思われません。あくまでも
丸は丸、四角は四角、という単純な視点に立っていただけと思われます。とにかくこの種のモノはそれほど世の中に溢れているモノではありませんし、更に加えて、目的が検査用機器ですから、美意識注入は論外だった筈です。とても「遊び心」を加えて作るスジの物ではありませんでした。
然し、それが逆に働くのか、現在の目で見る限り妙な飾り立てをしていない分
全体像がホントに新鮮に感じます。これは、この例に限らず、カメラでもクルマでも復刻版の名で往年の名機が蘇ってくる時に感じる新鮮さ
に似ていると思うのですがどうでしょうか。
このような製品を現在、実際に使用する事例は全くありません。従って、光学製品の博物館に収納されるのは当然としても、往年のドイツ・マイスターの傑作として、博物館とは雰囲気の違う豪華な応接間に置いておく、とか、美術館の展示場の片隅にさりげなく陳列しておく、とか、それなりに利用する事でも充分その存在感が発揮されるような気がします。むしろ、それらの方がふさわしい対応の仕方かも知れません。
もう一つ加えれば、普通の家庭の普通の場所に置くだけでも 勿論 間違った利用とは言えません。その方が日常の手入れが行き届く点で逆に歓迎すべき方法と言えるのかも知れませんね。形も姿も実に美しいのでいわゆるひとつの「西洋盆栽」と思えばよいのですから・・・。